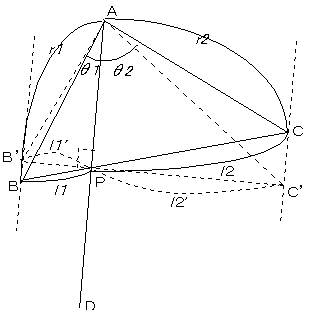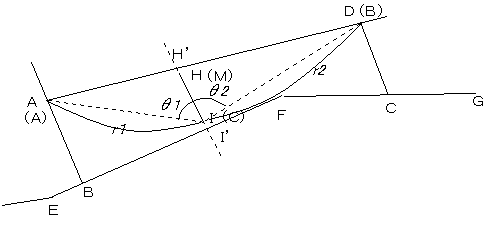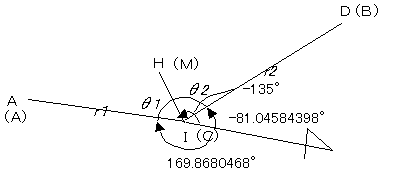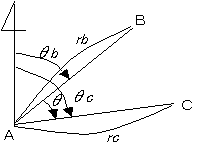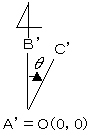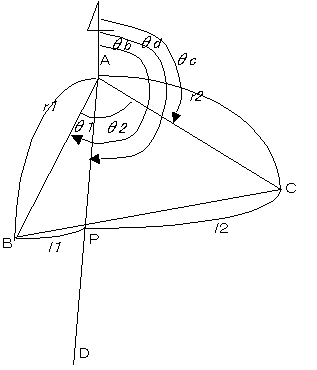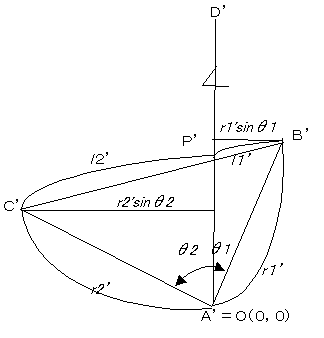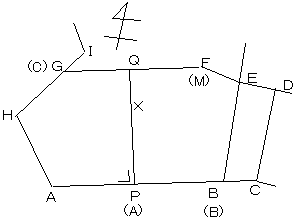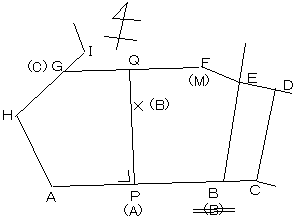本稿:H16.8.24追加
H17.2.25 5.3,54記述追加
H17.3.29 5.5記述追加
5.交点計算
筆者は方程式計算による交点計算はきらいです。
なぜなら、最初に立てた式から計算ができるように変換していくのに時間がかかるからです。
方程式計算で座標値を計算しなければならない点が二つもあるとそれだけでめげてしまう。
そこで、なんとか簡易な方法がないか探していたら8/24に見つかりましたのでここに記します。
交点計算がどこかの掲示板で話題になっており、筆者のホームページも紹介されておりました。
それに、刺激されてさらに考察を加えましたところいい方法がありましたので5.3以降に記します。
平成15年の問題型の交点計算方法を5.5に記述します。
5.1 交点計算の原理
|
直線ADと直線BCの交点Pを求める。
直線BCをl1とl2で内分する方法とする。
△APBの面積をS1、△APCの面積をS2とすると
l1:l2 = S1:S2
一方で直線APに対して直角の線を引いてBを通るAPに平行な線との交点をB’、Cを通るAPに平行な線との交点をC’とする。
これで、△APBの面積=△APB’であり、△APCの面積=△APC’の面積である。
なぜなら、B点及びC点を平行移動しているので等積変換しているだけであるから。
l1 :l2 = S1:S2 = l1' : l2'
l1' = r1sinθ1
l2' = r2sinθ2
∴ l1:l2 = r1sinθ1 : r2sinθ2 |
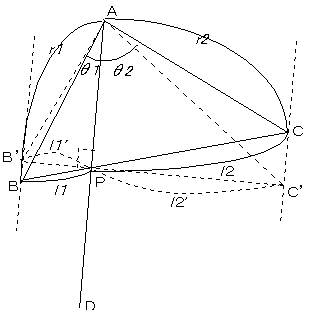 |
永田方式の計算方法ではr1,r2,θ1,θ2
が簡単に求められるので直線BCを上記の比率で内分すればよい。内分方法も既に確立しているのでP点がすぐに求まる。
5.2 交点計算の電卓操作
事例 平成14年の問題より
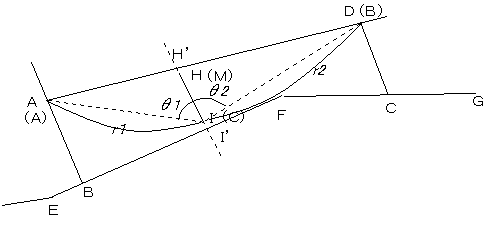 |
測量点座標一覧表 |
| 筆界点 |
X座標 |
Y座標 |
| A |
53.31 |
60.48 |
| B |
61.97 |
65.48 |
| C |
78.99 |
53.46 |
| D |
72.16 |
41.63 |
| E |
56.37 |
71.08 |
| G |
89.03 |
53.42 |
| H |
63.11 |
51.02 |
| I |
69.65 |
57.56 |
()は下記で使用するメモリへの割り付けを示している
直線ADと直線IHの交点H’を求める(直線ADを直線IHにより内分する。)
①計算の準備として座標値を各メモリに入れる。
A点をAメモリへ
D点をBメモリへ
I点をCメモリへ
H点をMメモリへ
②r1,θ1,r2,θ2を求める
☆下記の計算では角度は度分秒に直していないが、直す必要がないからです。桁数は度分秒と思ってすべて使用する。
| ・HIの方向角を求める |
|
|
M - C |
>r∠θ |
= |
|
 |
= |
∠-135 |
|
| ・r1,方向角を求める |
|
|
A - C |
>r∠θ |
|
|
|
= |
16.5988・・・ |
r1 |
|
 |
= |
|
|
|
|
∠169.8680468 |
方向角1 |
| ・r2,方向角を求める |
|
|
B - C |
>r∠θ |
|
|
|
= |
16.1265・・・・ |
r2 |
|
 |
= |
|
|
|
|
∠-81.04584398 |
方向角2 |
・求めた各方向角を図示すると下記のとおり
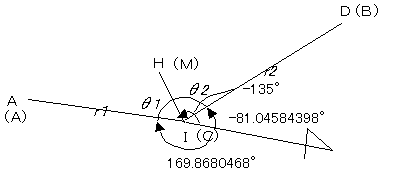
| ・θ1,θ2を求める |
|
|
|
|
θ1 = 360 -135 -
169.8680468 |
= 55.1319532 |
|
θ1 |
|
θ2 = 135 -
81.04584398 |
= 53.95415602 |
|
θ2 |
| ③ |
16.60×sin55.1319532 |
|
= 13.6198・・・・ |
|
r1sinθ1 |
|
16.13×sin53.95415602 |
|
= 13.04185・・・・ |
|
r2sinθ2 |
| ④ADを内分する |
|
( |
13.042 × |
A |
+ |
13.620 × |
B |
) ÷(13.042 + 13.620) |
= 62.9393・・ |
H’点のx座標 |
|
|
 |
|
= |
|
|
|
50.850・・i |
H’点のy座標 |
| ⑤座標値がHI線上にあることを確認しよう。 |
|
|
sharpのEL546Rの場合(☆電卓には得意と不得意があるようなので使い分けてます) |
|
|
 |
 |
3 |
1 |
|
|
|
stat1モード |
|
|
|
|
|
|
| H,Iの座標値を入れる |
|
|
63.11 |
 |
51.02 |
|
 |
|
|
n=1と表示 |
|
|
69.65 |
 |
57.56 |
|
 |
|
|
n=2と表示 |
| 確認する |
|
|
|
|
|
|
62.94 |
 |
 |
|
|
|
|
62.94y'=50.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HI線上のx座標62.94はy座標で50.85であることを示している。 |
コメント
本方法が方程式計算よりどれくらい早いかはこれからの使い込み次第です。
方程式計算は時間がかかりかつ短縮する方法はないが、この方法ではθ1とθ2の計算がややこしいが、図を書いて間違えないようにすれば確実に早くなると思う。
5.3 改良した交点計算の電卓操作
本稿:H17.2.25追加
①計算の準備として座標値を各メモリに入れる。
A点をAメモリへ
D点をBメモリへ
I点をCメモリへ
H点をMメモリへ
②r1sinθ1,r2sinθ2相当を求める --- 詳しくは5.4参照
| ・r1sinθ1相当を求める |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( A - C ) ÷ ( M - C ) |
= |
 |
= |
-1.472477・・・i |
r1sinθ1相当 |
|
|
|
|
|
|
|
↑ |
|
|
ACがMCより左にあり方向角がマイナスなのでマイナスの値。使うのは符号を無視した値。 |
|
|
|
|
交点となる真中の線で割る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
| ・r2sinθ2相当を求める |
|
|
|
|
|
|
( B - C ) ÷ ( M - C ) |
= |
 |
= |
1.4097859・・・i |
r2sinθ2相当 |
③ADを内分する
|
(1.4098 × A+1.4725 × B ) ÷(1.4098 + 1.4725) = |
62.9400・・ |
H’点のx座標 |
|
|
|
|
|
 |
=50.8499・・ i |
H’点のy座標 |
④座標値がHI線上にあることを確認しよう。
検算は5.2⑤のとおりに行う。
コメント
この方法なら1分以内に交点が求まるのではないか思う。
以前の方法に比べて、長い角度の数値をメモする必要がなくなった。
5.4 改良した方法の考え方
--- 解らなくても電卓操作ができればいいのです
(1)二つの線の間の角度計算
|
ABの方向角をθbとする。 |
|
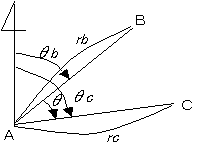 |
|
ACの方向角をθcとする。 |
|
|
この間の角度θは次のようにして求められることに気がつきました。 |
|
|
|
|
|
|
( C - A ) ÷ ( B - A ) >r∠θ |
|
この計算をすると、右の下の図のような変換をしたことになります。 |
|
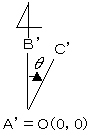 |
|
つまり、点ABCをABの線をx軸とするように全体の向きを変えたことになります。 |
|
|
|
|
|
OB’とOC’の方向角は図のとおりだとして |
|
|
|
それでは、辺長はどうなるかというと、 |
|
|
|
OB’の辺長 = 1 |
|
|
|
OC’の辺長 = rc/rb となります。 |
|
|
※わかったこと |
|
|
|
|
角度の引き算 |
|
二つの線分を割る |
|
|
|
角度の足し算 |
|
線分 × r∠θ |
|
|
|
|
|
|
rは辺長の倍率、θは足し算する(回転させる)角度
θがプラスだと右回転、マイナスだと左回転
(これは4.2で直角線を求めるのに使いました。) |
|
これを応用すると、右図のθ1,θ2が求められる。 |
|
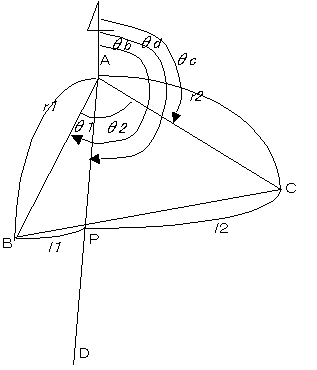 |
|
|
|
|
|
θ1を求めるには |
|
|
|
( B-A ) ÷ ( D-A ) >r∠θ |
|
|
|
|
|
|
θ2を求めるには |
|
|
|
( D-A ) ÷ ( C-A ) >r∠θ |
|
|
|
|
|
|
これでもう角度を二つ計算して、メモして引き算することから開放された。 |
|
(2)r1sinθ1,r2sinθ2の計算
|
線AB、線ACを線ADで割ると右図のように線OD’をx軸とするように回転した相似形ができる。 |
|
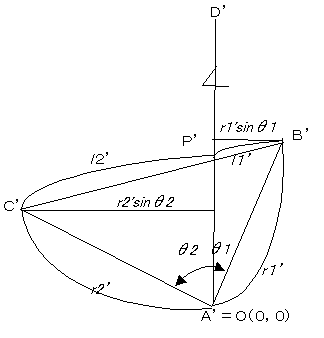 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OB’の計算 |
|
|
|
|
( B-A ) ÷ ( D-A ) |
--- ① |
|
|
OC’の計算 |
|
|
|
|
( C-A ) ÷ ( D-A ) |
--- ② |
|
|
|
|
|
|
|
次にr1sinθ1,r2sinθ2はどうなるかというと |
|
|
|
|
|
|
|
|
r1sinθ1 : r2sinθ2 |
|
|
|
= |
r1'sinθ1 : r2'sinθ2 |
相似形だから |
|
|
|
= |
B’のy座標 : C’のy座標 |
|
|
|
= |
①のyの値 : ②のyの値 |
|
|
|
|
|
|
|
|
これで交点計算に必要なr1sinθ1:r2sinθ2の比率数値がすぐに求まることになる。 |
|
5.5 平成15年問題型交点計算
本稿:H17.3.29追加
5.3にて改良した交点計算の方法を示しました。
その後に問題を解いていたら、ある辺に直交する線と他の辺の交点計算する問題がありました。
この問題への対応として次のとおりにするとよいので、以下に記します。
(1)問題
平成15年の本試験に出題されたものから交点計算のところだけをピックアップしました。
右の問題図と次の座表値から交点計算が必要なのはQ点です。
ABに直角なPQの交点のQの座標を求める。
|
測量点座表値一覧 |
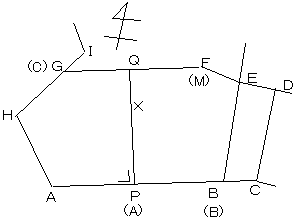 |
|
筆界 |
X座標 |
Y座標 |
|
A |
505.16 |
503.71 |
|
C |
517.81 |
525.62 |
|
D |
524.79 |
529.65 |
|
F |
530.91 |
515.47 |
|
H |
511.43 |
500.09 |
|
I |
530.91 |
500.09 |
| 15年の問題では上記の点だけ与えられており交点計算するに必要なG点とB点他の点は求めてくる必要があるが、その求め方は本題でないので、省略してB点、G点及びP点を次に記載する。 |
|
筆界 |
X座標 |
Y座標 |
|
B |
514.49 |
519.87 |
|
G |
522.03 |
500.09 |
|
P |
510.31 |
512.63 |
(2)考え方
5.1~5.4で記述した方法は4点の座標がわかっている場合の計算方法です。
本問の場合は、PQはABに直交するとしか解っていないので交点計算する点のうちPGFの3点しかわからない。線PQ上のもう1点がほしい。
はい、みつかりました。X点です。
X点は線BPに直交するB点と同じ長さを持つ点です。
X点の求め方は、4.2直角線を求める方法にて行なう。 その後は4点交点計算ができる。
(3)計算方法
①計算の準備として座標値を各メモリに入れる。(図中の括弧内に割りつけを表示)
P点をAメモリへ
B点をBメモリへ
G点をCメモリへ
F点をMメモリへ
| ②直角線上のX点の計算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B - A |
>r∠θ= |
 |
= |
∠60 |
--- 直角線ができたことを確認するのに使う |
|
|
|
|
|
|
|
|
( B - A ) × 1∠-90° + A = |
X点の座標 |
|
|
|
|
|
|
4.2②の式を辺長を変えない方法で左回りとして適用 |
|
|
|
|
|
|
|
すかさず、不用となったBメモリに入れる。 |
|
メモリ割りつけは右のように変わる。 |
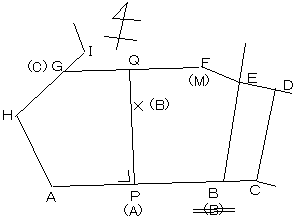 |
|
|
|
|
|
|
|
B - A |
>r∠θ= |
 |
= |
∠-30 直角線OK |
| ③内分比率を求める |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・GQの内分比率を求める |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( C - A ) ÷ ( B - A ) |
= |
 |
= |
-0.5980・・・i |
GQの内分比率 |
|
|
|
|
|
|
↑ |
|
|
|
|
GPがXAより左にあり方向角がマイナスなのでマイナスの値。使うのは符号を無視した値。 |
|
|
交点となる真中の線で割る |
|
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
・QFの内分比率を求める |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( M - A ) ÷ ( B - A ) |
= |
 |
= |
1.5262・・・i |
QFの内分比率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FGを内分する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( 0.598 × M + 1.5262 × C ) ÷ ( 0.598 + 1.5262 ) = |
524.5298・・ |
Q点のx座標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
504.419・・・i |
Q点のy座標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ④座標値がXP線上にあることを確認しよう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今回の検算は角度で簡易にやります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ans |
- |
|
A |
>r∠θ |
= |
 |
= |
∠-30 |
間違いなく直角線上にあり |
コメント
平成15年の試験は筆者も受験しました。この交点計算までの過程でへとへとになりました。ここまでにずいぶんと時間を使っていたのでした。交点計算は時間がかかるのでもうすっかり、やる気をなくしました。でも、もう大丈夫です。
戻る