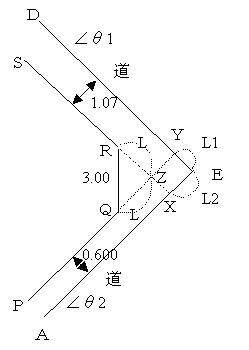 18年の問題の一番複雑なところは右図のような両側セットバックと隅切りでした。
18年の問題の一番複雑なところは右図のような両側セットバックと隅切りでした。他の箇所はこの問題の箇所の解法に含まれます。
線DEをセットバックした線SRと線AEの交点をXとし、線AEをセットバックした線PQと線DEの交点をYとする。さらに線SRと線PQの交点をZとする。
L1、L2、Lはそれぞれ図の辺長とする。
求める点はR及びS点であるが、直接に計算できないのでX点又はY点を求めその後にZ点を求めて、最終的にR点とQ点を求めることになる。
本稿 H18.9.3記述
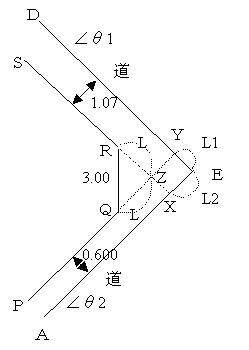 18年の問題の一番複雑なところは右図のような両側セットバックと隅切りでした。
18年の問題の一番複雑なところは右図のような両側セットバックと隅切りでした。
他の箇所はこの問題の箇所の解法に含まれます。
線DEをセットバックした線SRと線AEの交点をXとし、線AEをセットバックした線PQと線DEの交点をYとする。さらに線SRと線PQの交点をZとする。
L1、L2、Lはそれぞれ図の辺長とする。
求める点はR及びS点であるが、直接に計算できないのでX点又はY点を求めその後にZ点を求めて、最終的にR点とQ点を求めることになる。
 ここまでで求め方の主要なところを説明したので、次にL1,L2,Lの求め方を説明します。
ここまでで求め方の主要なところを説明したので、次にL1,L2,Lの求め方を説明します。
L1 = 0.60 ÷ sinθ (θは狭角)
L2 = 1.07 ÷ sinθ
L = 3.00 ÷ 2 ÷ sin(θ÷2)
これでR点とQ点が求まる。
通して電卓の操作を以下に記述します。
A,E,D点をメモリしてあるものとします。(現実にはEメモリは存在しませんので適宜、割付けたメモリに読み替えてください。)
arg((D-E)÷(A-E))=90 → M θ Mメモリに格納
0.60 ÷ sinM = 0.60 L1 90°なので省略できる
1.07 ÷ sinM = 1.07 L2 90°なので省略できる
3.00 ÷ 2 ÷ sin(M÷2)=2.1213 L
E + 0.60∠arg(D-E) + 1.07∠arg(A-E)= 120.387,121.389i Z点の座標値
Ans + 2.1213∠arg(D-E)= 121.89,119.89i → M R点の座標値 Mメモリに格納
式を戻して
E + 0.60∠arg(D-E) + 1.07∠arg(A-E)= 120.387,121.389i Z点の座標値
戻して式を修正
Ans + 2.1213∠arg(A-E)= 118.89,119.89i Q点の座標値
Ans - M >r∠θ = 2.9999 RQの辺長 OK
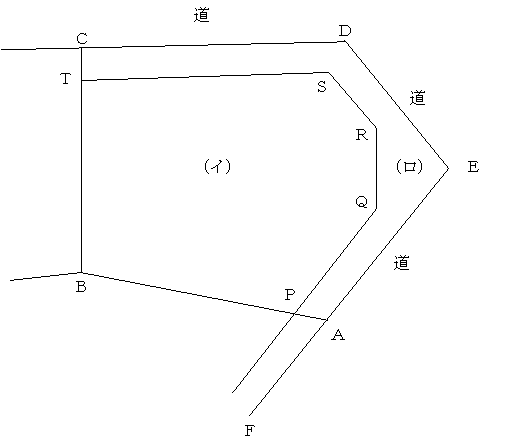 問題の他の点の求め方は次のとおりである。
問題の他の点の求め方は次のとおりである。
A点はF点からの距離と方向角で求める。
F+7.904∠arg(E - F)
P点はA点からの距離と方向角で求める。
A+0.630∠arg(B - A)
T点は片側セットバックでありC点からの距離と方向角で求める。
S点は両側セットバックであり、Z点を求める方法と同じである。
さて、面積と辺長の計算であるが、点の数が10点ありすべてメモリできないので、この部分にかなりの時間がかかるので一工夫がいる。
計算過程でABCDEの各点は順にメモリできる。PQRSTの各点は紙にメモする。PQRSTの各点をメモリする前にABCDEの各点をメモリしたものを使って辺長を求めておこう。次にロの部分の面積は6角形と5角形の二回に分けて面積計算する。イの部分の面積計算は6角形の面積計算で計算する。これでかなり早く計算できることになる。