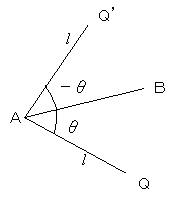6.1 abs関数とarg関数の位置付け
B - A = Δx + Δyi >r∠θ= r ,θ
↓ ↓abs argで各別に取出しできる。

6.2 abs関数とarg関数の使用例
A+(B-A)÷abs(B-A)×l∠±θ= Q又はQ’
-------------------- ------
↑AB線を長さ1とする ↑角度を±θ だけ回転し長さをl とする
又は
A+l∠(arg(B-A)±θ)= Q 又はQ’
----------------
↑線ABの方向角に±θ し長さl の点を求める。
プラスは右回り、マイナスは左回り
・AB線を基準として長さl の直角の点を求める
上記の式に90を入れればよい。
A+(B-A)÷abs(B-A)×l∠±90= Q又はQ’
この式は4,2の式と同じ
又は
A+l∠(arg(B-A)±90)= Q 又はQ’
プラスは右回り、マイナスは左回り